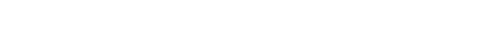感動の灯火
地方において地場産業や伝統工芸などの再生についてのお仕事や、講演の講師をさせていただく機会があります。 状況として多いのは、数百年にわたり続いてきた伝統的地場産業が衰退の危機に瀕している状況です。 機能としてのみの製品の役割は、最新技術の出現により代替製品にとって代わられており、「芸術品」としての付加価値で生き残っている製品が多い状況。 例えば、「わらじ」という歩くために足を保護する機能を持った履物がありましたが、今やスニーカーや革靴、サンダルに取って代わられて流通市場で見る機会は少ない現状です。 伝統工芸で多いのは着物などの布もの、食器、籠やおもちゃなどが多いですが、それらの機能での優位性はとっくに新技術製品に明け渡し、今は「芸術品」などに昇華しきれたものしか市場に存在していません。 一方、今日存在する生き残った製品は数百年間という長い間人々に感動を与え続け、時代に淘汰されずに人から人に伝えられ、息づいてきた「感動の証明」であると思います。 機能を越えたところにある付加価値、「歴史」や「伝統」、「物語」、そして「感動」は簡単に出来るものではありません。 またその感動の灯火を、私たち世代で消してしまうのか次世代まで伝えられるのか、非常に責任重大なことと感じています。
テーブルウェア・フェスティバル
知人よりお誘いをいただいて「 テーブルウェア・フェスティバル」に行ってきました。 http://www.tokyo-dome.co.jp/tableware/ この展示会自体、また東京ドームで催される展示会に行くのは初めて。 外野席からグランドを見下ろしたときに、観客席に囲まれたグラウンドのなかにある、きらびやかな箱庭みたいな街を見て綺麗だなと思いました。 食器やテーブルコーディネートなど、お料理に興味がある人にはたまらない催しと思います。 夕方遅く行きましたが結構混んでいました。 日本および世界の有名な食器の生産者が一堂に会していたり、作家さんから直接新製品やレアモノがお安い値段で買えたりします。 普通の店にないような良いモノをお得にと探している人には良いかもしれないですね。 ...
自己超越!?
年末に大阪で「贅沢野菜のバランスランチ」という美味しそう!な宅配ランチの事業をされているFさんにお会いしたとき伺った面白い話です。 http://www.cafesante.jp/(大阪市内にお勤め・お住まいの方は是非!)http://www.ippo-project.com/ Fさんは現在はソシアルアントレプレナーという立場ですが、以前に心理学も研究されていたそうです。 ...
充電
ちょっとお休みをいただきまして、南方に行って参りました。
××カルチャーを造る
新規事業を造ったり、何かビジネスをするときに究極の目標はカルチャーを造ることなのかなと思います。 いわゆる「そのもの」を取り巻くムーブメントやブームが起きて、それが文化となるといった感じ。理念のような考え方が中核にあって、それを取り囲んでいく様々な要素。 遊び、趣味、楽しみ、生き方、仕事、生活、商品、サービスそのもののバラバラに存在しているものが、それらを取り巻くスタイルや様々なものの塊としてのファッションやカルチャーとなるという感じです。 例えば、ロックカルチャー、サーフカルチャー、ヒッピーカルチャー、モーターサイクルカルチャー、パンクカルチャー、シリコンバレーカルチャー、アメカジカルチャー、漫画カルチャー、アキハバラカルチャー、ロハスカルチャー・・・・ 単品で存在するものを、社会のうねりに混ぜながら怒涛のムーブメントを巻き起こし、一連の社会現象、象徴としてしまう。 特にアメリカ人がうまいですよね。10年ぐらい前に起こった、ITブーム時代のCRM、SCMといった塊としてのムーブメント、近年で言えばLOHASといった感じで、市場を形成する要素としての一塊を造ってしまうと関連商品の市場が大きくなる仕掛け作り。 カルチャーが出来上がる要素としては、「××族」の出現、マニア、評論家の出現、カルチャーを象徴する雑誌の出版、象徴する音楽、ファッション、集会、コミュニティの発生などです。 また、そのカルチャーを造ろうと思って取り組んでいると、単なる製品開発を行うよりも面白いということがあります。 例えば、ミニカーを開発していたとしても、ミニカー総本山の台東区のイベントに、ミニカースタイルの「ミニカー族」が終結し、ミニカーサウンドのライブなどをミニカーゲームに盛り上がる夜は更けていく。ミニカーカルチャーは1964年ごろおもちゃメーカーである・・・・ それが豆腐でも良いし、自然化粧品でも良い。 ...
お薦め本
最近、企画・編集のお仕事をされているお友達の方から本を頂きました。 とても面白い本なのでご紹介したいと思います。 ...
10年前、10年後
知人の年初のブログに「10年前の自分は~」ということが書いてありました。 ...
インプットとアウトプットの関係
最近プランニング系の仕事の中で、良いアウトプットをするにはということをよく考えます。今日はインプットのことについて少し。 色々なアイデアを出すにはたくさんのインプットがあればあるほど良いのだろうな~とつくづく思います。まさに、アウトプットの質と量はインプットの質と量に比例する 色々と仕事と勉強を重ねていくと、いつの間にかビジネスやマーケティングなど基礎の理論や考え方は、自分の中で消化されて思考のプラットフォームができ、物事が効率よく精度を上げて考えられるようになります。(これもノウハウがあるのでまた後日) そしてやっぱりアウトプットに効いてくるのは、様々な情報のインプット。 新しい事業のアイデアを思いつくときには不思議と、毎月立ち読みしている雑誌、毎日なんとなく読んでいる新聞、何気なく見ていたテレビや、たまにしか見ない日経産業新やMJの記事から得た、ほとんど憶えていないような情報がネタにつながる気がします。忘れていたことを思い出し、テーマにあわせてイメージとなっていく。 最近特にゼロベースから何かを創造するという課題をこなしていくうちに、インプットはアウトプットに直結するんだな~と実感しています。 とにかく、たくさん人に会う、現場100回、何でも経験してみる、話題の店や場所には必ず行く、高級そうなところにも行ってみる、お薦め本は読む、毎月本屋で全ての雑誌を立ち読みする、新聞は見る、気になったことは全て検索する、行けるだけの場所に旅行に行く、できるだけのスポーツに挑戦する、海外のトレンドや文化を紹介するテレビは出来るだけ見る、各地の歴史を研究する、ポップカルチャーを研究する、最新のファッションを研究する、気になるものの歴史やディテールを研究する・・・・・ 平等に持っている限られた時間で、いかに多くのインプットをするか! ...
熱い銀世界
先週会津若松に行ってきました。 東京や大阪では雪を見ないこの冬ですが、郡山から猪苗代方面に走り出したら一面の銀世界。 遥かに見える山々は威風堂々といった様相です。
「生きるって決めたんだよ」
本日(日付が変わってしまいましたが)、先輩のKさんに素敵な方をご紹介していただきました。 Hさんといって独立して数十年コンサルティング会社を経営されている方で、面白い事業をたくさんされている魅力的な人でした。 ものすごく多くの含蓄ある言葉をいただきましたが、今晩はその中で極めつけの一つを記しておきたいと思います。 太平洋戦争終結から29年目にしてフィリピンルバング島から帰国を果たした小野田 寛郎さんのお話。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E7%94%B0%E5%AF%9B%E9%83%8E ...