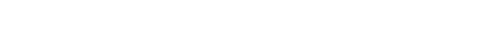2.個性を活かすマーケティング入門 ⑨うわさになるプロモーション
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」~弱みを強みに転じる生き残り方~2.個性を活かすマーケティング入門 ⑨うわさになるプロモーションだれでもできるプロモーションのやり方 いま新しい製品やサービスの認知拡大に効果的なのは、雑誌や新聞等の「パブリシティ(記事)」で多く扱ってもらうことです。最近は、テレビのCMや新聞の全面広告よりも記事のような形で取り上げられるほうが、広告を敬遠する消費者に注目されるようになって来ました。 雑誌や新聞に多く出ている製品は注目されますし、何か公に認められた感が出て信用力も得られます。話題となりネット上の口コミも生じ、さらには掲載記事が営業時や店頭での販促ツールにもなります。 各メディアへのアプローチ方法は、資料送付を雑誌社編集部・新聞社等に対して行います。この活動を「プレスリリース」といいます。また、「キャラバン」といって、雑誌社などに商品を持って説明をしにいく方法もあります。自らの製品のコンセプトや優位性をまとめた資料を作成し、分かりやすくニュースを伝えるのです。 ...
2.個性を活かすマーケティング入門 ⑧チャネル(販路)は最終ターゲットに届ける手段
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」~弱みを強みに転じる生き残り方~2.個性を活かすマーケティング入門 ⑧チャネル(販路)は最終ターゲットに届ける手段チャネル(販路)構築のポイント いくら良い製品でも、ターゲットにした人が便利に買えるところで売っていないと買ってもらえません。日本市場の販売チャネルとしては、小売店販売、通信販売、業務用販売など多様な流通経路がありますが、今回はメーカーとして小売店舗を通じて販売するという設定で、いくつかのポイントを挙げていきます。 メーカーサイドからしますと、チャネル(販路)はあくまで最終ターゲットに届ける手段であり、卸売業者や小売業者はお客さまでもありますが、厳密に言えば「販売パートナー」です。たまに、流通業者さんにものを納めたらそれで終わりと思う製造業の方もいらっしゃいますが、そうなるとお店で売れないと一回の出荷でビジネスは終わってしまいます。共に、ビジネスパートナーとして共通のお客様にお届けする方法を一緒に考えていく必要があります。チャネル(販路)はどうやって探すの?小売店チャネルの探し方は、小売店の売上げ順リストなどが掲載されている「日経MJ」などの書籍や、「競合他社製品のホームページの取り扱い店舗リスト」等を活用します。 ...
2.個性を活かすマーケティング入門 ⑦ドンピシャ価格を狙う
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」 ~弱みを強みに転じる生き残り方~ 2.個性を活かすマーケティング入門 ⑦ドンピシャ価格を狙う ...
2.個性を活かすマーケティング入門 ⑥その製品・サービスに魂はあるか
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」~弱みを強みに転じる生き残り方~2.個性を活かすマーケティング入門⑥その製品・サービスに魂はあるか 商品をして語らしめよ資生堂の社訓で、「商品をして語らしめよ」という言葉がある、とファッションジャーナリストである川島容子さんの著書「資生堂ブランド」で知りました。とても素晴らしいと思います。製品というアウトプットにするまでに多くの想いや苦労、ウンチクなどがあると思います。しかし、その製品を買うお客様が手に取るのはその商品です。その製品に想いやそのブランドにある背景などすべてが詰め込まれた状態にできることが、一つの成功と思います。触れたらしびれるような「魂のこもった製品」は、単なるモノではなくなります。その製品を手にとったらしびれてしまうような感覚を持たせられれば素晴らしいことと思います。歴史に残る名品は、必ずその要素があると思います。芸術作品はそうですし、量産製品でも名だたる海外ブランドの製品であったり。自分は車が好きですが、乗っただけでしびれてしまう特別な車が存在します。ターゲットであるお客様にとって、感動を与えるような背景、ストーリー、作り手の情熱を持った製品を目指していくことはとても大切です。 そのためにはどうしたら良いのか。それは「徹底的に全力をかけてものづくりを行っていく」、これが全てです。 チャッチャと効率を求めて、手間かけず安く簡単に済まそうとラフに作ったものは、人の心には届かず儚く終りを迎えてしまいます。粗い仕事は自分の人生も粗いものにしてしまいます。 自分の名前のブランドとして取り組むたとえば作ろうとする製品やサービスなどのすべてのアウトプットを「自分の名前のブランド」と考えてみてください。「卒業制作」のように自分の名前で全責任を負うとなると、つまらないアウトプットは行いたくなく、取り組む姿勢がまったく変わるでしょう。それは、小さなチラシやサンプルなどの販促物や日々のレポートなどにも言えることです。会社や組織の仕事でも、小さなことでも全て自分がやる以上は、自分のアウトプットそして生き様なのです。 全力をかけて自問自答しながら納得のいく恥ずかしくない仕事をとことんすること、そして人生の一こまをベストを尽くして生きること、これが製品やサービス、全てのアウトプットに魂を宿らせる秘訣です。つづく
2.個性を活かすマーケティング入門 ⑤自らの個性を最大化するマーケティングミックス
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」~弱みを強みに転じる生き残り方~2.個性を活かすマーケティング入門 ⑤自らの個性を最大化するマーケティングミックスターゲット・ニーズ・独自能力を軸に事業領域・コンセプトをまとめたら、その後は具体的なアウトプットとして、ものごとを提供していきます。その提供方法を「マーケティングミックス」というまとめ方をします。そのミックスは、4つのPで始まる文字で構成されます。「プロダクト・製品」、「プライス・価格」、「プレイス・流通チャネル」、「プロモーション」です。 事業領域・コンセプトをまとめた、ターゲットの持つニーズそ解決するために、どのような製品・サービスを、どういった価格で、どのような流通チャネルを用いて、どのようなプロモーションを行って、独自の方法で「解決策」を提示していくかということです。また大切なのは、4つのPはあくまで「手段」に過ぎないということを常に認識する事です。個別のやり方にこだわりすぎると事業の本質を見失うことにもなります。そしてここでも重要なのは、「思いやり」です。その製品で、その価格で、その販売チャネルで、その伝え方が本当にターゲットの方に対し最適なのか、自問自答を繰り返しながら作り上げていくことが大切になります。つづく
2.個性を活かすマーケティング入門 ④絶対に負けない戦略とコンセプト
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」~弱みを強みに転じる生き残り方~2.個性を活かすマーケティング入門 ④絶対に負けない戦略とコンセプトどんな事業、製品・サービスをつくっていったらいいの?以上のSWOT分析を行い、前提を整理した後に、何をやるべきかを考えます。実際に自分たちがどのような事業を行っていくのかということです。そのために、事業領域やコンセプトをまとめていく必要があります。事業領域、コンセプトの作り方自社の強み、弱み、機会、脅威を整理しそれをもとに、「事業領域」をまとめます。事業領域とは「事業ドメイン」ともいい、自社の行うべき事業のことをいいます。また、この事業領域を製品やブランド開発等の場合、「製品コンセプト」・「ブランドコンセプト」として置き換えても良いです。事業領域 ターゲット・ニーズ・独自能力 事業領域・コンセプトは、「ターゲット、ニーズ、独自能力」といった軸で組み立てます。 強みやチャンスを活かし弱みやピンチを補う、自分だけが出来る組み合わせを見つけ出し、「勝てる個性」を具体的に強調していきます。人にそれぞれ個性があるように、世界に一つの強い個性を持った事業・製品に仕立て上げることが出来ます。 ...
2.個性を活かすマーケティング入門 ③彼を知り己を知れば百戦危うからず
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」~弱みを強みに転じる生き残り方~2.個性を活かすマーケティング入門 ③彼を知り己を知れば百戦危うからず それでは、まず第一に現状を把握するというプロセスからはじめましょう。孫子の兵法に「彼を知り己を知れば百戦危うからず」という格言がありますが、これは戦やビジネスの真髄です。自分とは何なのか、自身を取り巻く環境とはどうなのかを徹底的に知れば、どんな戦いでも負けることはないというのです。まず自分自身の内部環境の分析、自分を取り巻く外部環境の分析をとことん行うことが大切です。内部環境とは、「人材」、「組織」、「パートナー」、「資金」、「技術」など。外部環境とは、「市場」や「競合」、「経済」、「政治」、「法律」、「自然環境」などです。何か難しい感じですが、とにかく回りを見て、自分を見ろということです。 これをとことん事実に基づき具体的に調べていきます。その方法は、書籍、マーケティングデータ、インターネットなどから、また実際のビジネスの現場です。よく「現場100回」という言葉がありますが、ビジネスの答えは現場にあります。とにかく現場を見ることが最も重要、机の上では何も本当のことは分かりません。売場、生産現場、使う場所などの現場を100回以上見て、事実を把握していくことが大切です。 そして、それを「SWOT分析」という手法でまとめていきます。非常に古典的なアプローチですがとても整理しやすいのが特徴。内部環境として「S(ストロングネス・強み)」、「W(ウィークネス・弱み)」、外部環境として「O(オポチュニティ・機会)」、「T(スリート・脅威)」を、一つの紙にまとめていきます。そして、自社の強みや弱み、チャンスやピンチを明確にしていくのです。 ...
2.個性を活かすマーケティング入門 ②作る・売る・伝える、すべてはつながっている
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」~弱みを強みに転じる生き残り方~2.個性を活かすマーケティング入門 ②作る・売る・伝える、すべてはつながっているよく福祉の現場や企業でも以下のようなことを聞く機会があります。「販路さえあればうまくいくのに」「製品は開発して出来上がっているがどこにどう営業したら良いのか分からない」「この商品誰が買ってくれるのか?」 よくあることですが、それぞれのマーケティング活動がバラバラになっているために起きてしまう問題です。聞き返したい質問は「それではこの製品を誰のために作っているのですか?」ということです。 誰のためでもないものは、きっと誰も要らないものでしょう。 すべてのマーケティング活動は前出の図のようにつながっているのです。「誰のためにどのような製品・サービスを、どのような方法で提供するのか?」それを詳細まで考えて、実行する。それがうまく機能しないと、一部の営業を強くする、広告を強くする、製品を開発するといった個別機能の増強では全体のビジネス活動はうまくいきません。また、事業がうまくいかないときも前述のマーケティングの図を見て原因を考えます。全体戦略や取り組みの中で何が足りないのか、どうしたらうまくいくのかの対策を練るのです。くれぐれもシンプルな図で示したように、全てのマーケティング活動は「有機的につながっている」ことを肝に銘じてください。マーケティングに関連する仕事をしている自分自身の事業会社でのキャリアもこのチャートに中に当てはまります。キャリアのスタートは、「プロモーション戦略」の一機能である「人的販売」、つまり営業の仕事です。その後商品の仕入れ担当者となり、「プロダクト・製品戦略」や「プライス・価格戦略」に携わり、その後ブランドの立ち上げで、販促や広告も含めた「プロモーション戦略」全体、また「チャネル・流通戦略」に取り組んだ経験をしました。多分多くの方がこのマーケティングのフレームワークの中の特定部分を中心に担当していると思います。 すべては、目標を決めて、大局的なビジネス全体を見据えた上で各戦術を実行することに成功の確率が高まります。 そしてみなさまの日々行う「営業」や、「調査」、「広報・広告」、「商品企画」、「お客様対応」などはマーケティング活動の一部であり、バラバラに行われるべきではなく大きなマーケティング戦略に基づいて繰り出されるべき一手、そして各自が行うべき活動は全体戦略に合った活動であるべきなのです。それらの戦略を関係者全員で共有して行くことも大切です。よって何の計画もなく出来るものをつくった後に、売先があれば売れるのに、どんな人が買うかわからない、といったことは本末転倒な話です。そうなると、「販路さえあれば売れるのに」、「どんな販路が良いのか?」、「どんな雑誌に載せればいいのか?」、「価格はいくらにしたらいいか?」、「どんなデザインがいいのか?」「製品コピーのフォントの大きさはどうしよう?」などということが、後から出てくることはありません。すべては「ターゲットとするお客様が喜ぶことを選ぶ」という答えです。 誰のために作って、伝えて、買いやすいように提供するという戦略を立て、個々の事が全体としてつながってこそビジネスはうまくいくのです。つづく記事一覧(こちらのページの下に、記事の一覧があります。そちらから続きをご覧ください)https://trife.co.jp/category/③コラム「障がい者施設の事業戦略-社会的弱者に/
2.個性を活かすマーケティング入門 ①超シンプルなマーケティング戦略策定のフレームワーク
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」 ~弱みを強みに転じる生き残り方~ 2.個性を活かすマーケティング入門 さてこれからは、授産施設の製品の販売において、また一般的なビジネスや個人の生き方にも参考になる、実践的なマーケティングの基礎知識について、シンプルにご紹介していこうと思います。 ...
1.障がい者が社会とつながる仕事 ④職場は「生きる場」
「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」 ~弱みを強みに転じる生き残り方~ 1.障がい者が社会とつながる仕事 ④職場は「生きる場」 ...