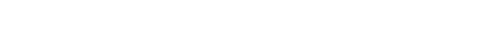先日、セルザチャレンジのメンバーでもあり、オニオンキャラメリゼを手掛けるプラスリジョン代表の福井さんにお声掛けをいただき、長野県松本市のアルプス福祉会にて、「授産施設のマーケティングセミナー」を行ってまいりました。
30名ほどの施設の職員の方々にお集まりいただきました。
日本全国各地の授産施設では障がいをもつメンバーが施設職員の支援のもと、日々ものづくりや作業を行い、仕事を通して社会とのつながりを得、人としてのやりがいを得、努力の結果収入(工賃)を得るべく頑張っています。
*授産施設:身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者、ならびに家庭の事情で就業や技能取得が困難な人物に対し、就労の場や技能取得を手助けする施設。全国に約8000箇所ある。
障がい者が働く現場へのマーケティングセミナーでは、ビジネスマンではない方むけに分かりやすい基本的なビジネス知識と、一般企業とは全く違う背景のある障がい者、授産施設のもつ事情を考えた、より精度が高く特殊な条件下で具体的な売り上げという結果の出る具体的なお話、にフォーカスしていきたいと常に考えています。
福祉の現場では、一般ビジネス以上に難しい取り組みに挑戦しています。
知的・精神・身体にハンディを持った障がい者、および物販ビジネス競争を日々行っていない社会福祉法人、ビジネスではなく福祉の専門家である職員のみなさまが、競争社会の中で切磋琢磨している一般営利企業、ビジネスマンと同じマーケットという土俵で、いかに互角に「モノの販売」を行っていくのか。
ビジネスとは本当に厳しいものです。
一般の企業でもこの国際競争の現代、最先端の技術や人材を集結した企業が、生きるか死ぬかのせめぎ合いの中で事業を立ち上げ、継続している状態。
その市場で社会的弱者による「モノの販売」に本気で挑戦していくことは、正気の沙汰なのか?
その目的は何のためか?そんなことはできるのか?やると決めたならどうやって成果を出していくのか?
今回のセミナーで自分自身も深く考え、戦略の方向性をまとめる良い機会となりました。
また、先日のネパール・バングラデシュ出張で、フェアトレードという面での社会的弱者・貧困層のマーケティングということについても戦略立案と実践、仮説と検証を繰り返した中でやっと見えてきたことがあります。
こんなことを書いているのは、実際に授産施設の障がい者や、発展途上国で援助や開発から取り残された本当に貧困にあえぐ人たちが携わるものについて、マーケティング活動を行い、純然にビジネスにしようとしているプロフェッショナル・ビジネスマンはほとんどいないのではと思ったからです。
理由は、それではビジネスにはならず食えないから。真実を追求し、弱者への支援を突き詰めれば突き詰めるほど、ビジネスの競争原理から乖離していくから。きれいごとでは生きていけないから。
プロボノの場合ビジネスのプロはボランティア活動として企業からのお給料をもらいながらの余暇活動ですし、社会福祉法人・授産施設の職員の方は障がい者の利用による国からの利用料で給与を得ており物販からの収入はありません。また、NGOは寄付や助成金で成り立ち、フェアトレードのみをビジネスとしている企業も収益性・効率性を確保するため、すでに途上国の中でも成長した競争力のある製品が作れるフェアトレード団体や企業との取引を推進しているのが現実です。
自分自身もできていないことですが、実際に当事者(働く障がい者や貧困にあえぐ人)と同じ、働いたら収入が得られ・そうでないと得られないという、他に収入源のないシビアな立ち位置にいないと、多分ビジネスとして真剣勝負にはならないような気がうっすらしています。
本当に仕事をするのが難しく一般就労が進まず授産施設で働くことになる障がい者、援助や経済発展から取り残され続け仕事が全くない貧困にあえぐ人々。
どこまでもその取り残された人々のために、仕事を作り、競争力を持った製品を作り、販売して、収益を上げ、利益を分配し、現状から送り出していく取り組み。
社会活動とビジネスとの融合。
今はそのことにフォーカスし、また好きなその活動を追求しながらビジネスとの融合を模索し、欲張りにも何とか生計を立てていこうと目論んでいます。その両立は結構難易度が高くて、悩みながら試行錯誤中です。
まあ、ビジネスマンとして人生を歩んできた自分が、障がい児を授かったことで得られたやりがいと大義、人生の使命として取り組めるテーマとして感謝していることなのですが。
というわけで今後、セミナーで話していることをもとに「社会的弱者のマーケティング」というテーマでブログに文章をおこしていきたいと思います。
そのまま書籍になったらいいな、なんて。
また、全国の授産施設や法人、フェアトレード団体の職員の方々からのニーズがあれば、セルザチャレンジの事業としてセミナーも実施していきたいと考えています。
「社会的弱者のマーケティング」、予定の見出しはこんな感じ
・授産施設にはビジネスのプロはいない
・一般企業にコスト競争力は勝てるか
・進む一般就労と施設で働く障がい者
・仕事づくりと職員のモチベーション
・授産施設は何を目標にすべきか
・授産製品成功のための方向性
フェアトレード編
・フェアトレードとは何か
・海外支援は国益か
・援助とビジネス
・フェアトレードの課題
・フェアなビジネスとするために
・ フェアトレード成功のための方向性
両方
・社会的弱者のマーケティング
・マーケティングのフレームワーク
・社会的弱者のための事業ドメイン・商品コンセプト
・品質で競争したいは幻想か
・チャリティーかビジネスか
・共感する人のみが顧客
・モノの販売において大切なこと
・社会活動とワーキングプア
・やるからには成果を
・事例紹介
・・・・・
って感じです。 ぼちぼち行きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
「社会的弱者のマーケティングセミナー」など聞いてみたい方はご連絡ください。
障がいがありながら働く意思のある人に仕事を通じたやりがいと社会とのつながりを。
障がい者を子供として、兄弟として、親としてもつ人に生きる力を。
様々な事情で貧困にあえぐ人々に生きるための仕事とお金を。
それを救える力を持つ人たちが手を差し伸べること。
静かですが、日本や世界に取り残された課題はたくさんあります。
そして今すぐにでも、みなそれぞれの身の丈で、何かできることがあると思います。