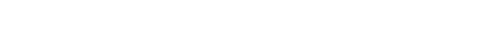慶応義塾大学院の政策メディア研究科、社会イノベータコース「ソーシャルビジネスの商品開発とプロモーション」という授業にお招きいただきお話ししました。
自身がソーシャルビジネスをはじめたきっかけや、究極のビジネス志向からの価値観の変化、試行錯誤と道のり、最近のセルザチャレンジの社会活動やソーシャルブランド・商品の立ち上げ事例について短い時間でしたが、紹介させていただきました。
時間的にいろいろなことを十分伝えられなかったですが、社会活動に非常に意識の高い人が多く、こちらも大変刺激になりました。方向は様々ですが、近い価値観や求める真実を持っていると思います。10年後とかみなどうなっているのかな?ともに未来を歩んでみたいです。
ある事業はソーシャルなのか?そうでないのか?、組織形態が株式会社で営利も追求しているのでソーシャルビジネスではないよね?、などの議論がよくあるようですが、全ての事業は営利でも非営利でも社会的貢献の側面がないと成り立ちません。
ソーシャルビジネスで最も重要なのは、ビジネスモデルや営利・非営利ではなくアウトプットとしての社会的インパクトの大きさです。
営利の大企業もソーシャルカンパニー・ビジネス。戦後の日本からトランジスタラジオを輸出したソニーはフェアトレード会社、目立ったCSR活動はしていないが法人税を多額に払っている大企業はソーシャルカンパニー。小学校はソーシャルインキュベーター。
マイクロファイナンスも儲かってますし、本当にお金を必要としている返済可能性の低い人に貸しているかは疑問?H&Mなどの縫製品は最貧国のバングラデシュなどで生産されてますが、フェアトレード製品?環境関連ビジネスはソーシャル?
難しいですね。
そして単に貧乏して個人ベースや小組織でやる商売がソーシャルビジネスでもないのです。
今学生の方に注目されるソーシャルイノベータとは、企業の就職難や行政および大規模NPO組織のサラリーマン化した閉塞感に対し、そのヒエラルキーから外れ、社会的活動を自ら飛び回って過ごすプレイヤーへの憧憬と思います。いままで注目されていた営利追求型ベンチャービジネスの不振という背景もあります。
ベンチャー企業のように自らが代表となり、社会のためになる活動を具体的にすぐ始めること。大きな組織の中で何年も働いてチャンスを得るのではなく、即国内外の現場で活動を始めること。
現在のソーシャルビジネスのプレイヤーは様々な人がいます。しかし多いのはやはりある程度社会経験というか、ビジネス経験を積んだ人が多いと思います。ひとつの事実は、稼げる力・ビジネスの力がないと事業の継続性や社会へのインパクトも得られないことです。
社会的に解決できていない課題というのは、なかなか難しいものばかりが残っています。もし大企業や行政としてではなく、小規模なソーシャルベンチャーとしてその取り残された事のためにコミットして、真の解決を求めて活動していく場合。果たして継続できるのか、経済面と折り合いがつくか、事業で収益が得られるか、資金調達は維持できるか、活動家としては食っていけるか、生計を立てていけるか。
自分自身は試行錯誤の毎日ですが、現在2つのアプローチで社会活動とビジネスの融合に挑戦しています。
1つはセルザチャレンジとして。純然な社会活動の事業継続のために、どう稼いでいくかのアプローチ。
完全なボランティア活動として無報酬で障がい者施設の作るものを売れるように考え、デザインし、流通を組み立て、プロモーションして販売支援するというセルザチャレンジの活動。
当初は、メンバーのできること、資金面ではポケットマネーでの運営でしたが、プロジェクトが大きくなり工数もかかるようになると片手間ではできなくなりつつあります。
資金のない中で実質行動をメインに置いた活動で実績を作ってきましたが、登記やオフィスなどの体裁を整えない状況では、あるスポンサー企業からは実際にはお金は出せない、経由して施設などに直接支払いたいという例もあります。
その他、資金調達の方法を模索しましたが、寄付・助成金での運営は難しさを感じ、現在は販売活動の商流に入ることで、「販売する」という自らの本分の活動で事業運営・継続のための資金を生み出そうとしています。
現在は資金的には困窮していますが非常に素晴らしいメンバーが集結してきました。本当に社会的意義のある活動の継続のために、WEB販売や小売店の展開など新しい収益の獲得方法に挑戦しています。
2つめはインフィニストリアなどのソーシャルブランドビジネスとして。純然なビジネス活動にどう社会貢献を織り交ぜるかというアプローチ。
もともと自分自身は株式上場を目指すベンチャー企業で2005年にアグロナチュラでスタートしたこの取り組みですが、インフィニストリアも同じく、営利追求活動のバリューチェーンの中に社会貢献活動を差し込みます。最近はコーズマーケティングとして一般的になりましたが、まずは売り上げの一部のNGOなど社会活動を純然に行う外部団体への寄付。ここまではただのチャリティ。
オーガニックコスメの製品そのものの生産は一般工場での生産ですが、その他の生産物としてカタログなどの印刷を福祉作業所に依頼する、発送業務などの軽作業を障がい者施設に依頼する、など。チャレンジトレードとなり、社会インパクトが増す。
プロダクトへのソーシャル比率が増した例が、オニオンキャラメリゼやShe with Shaplaneer、UDフロアなど。オニオンキャラメリゼはプラスリジョン社の福井さんが手がける発達障害のメンバーが作る玉ねぎ調味料。Sheはフェアトレードの製品ですが、手作り石けんの製作、パッケージの紙の手漉き、シルク印刷、箱組立、など製品の生産面も社会的弱者が担う。友人の桑波田君の開発するUDフロアは視覚障がい者のための室内での誘導するための床パネルで、調査研究に視覚障がい者が深く関与、また生産面での障がい者の関与も目指している例。ソーシャルプロダクトとなり、社会インパクトがさらに増す。
この2つのアプローチが交わり、社会的な活動でビジネスとして成り立っていく、自分自身が真実と思える活動を行いながら生計を立てていける、そんな未来を作っていければと考えています。
実際にビジネスの最前線は厳しく、生き馬の目を抜くえぐい話などもあります。人のために貢献したい個人個人の想いはあっても営利組織のサラリーマンとしてや金が絡むと別であり、きれいごとだけではいかない世界で闘っていけなくてはいけません。
一方澄んだ心の非常に優秀なNPO職員の方のお給料が一般企業よりも少なくてびっくりしたり、家族ができたらお金の問題で一般企業に就職するNPO30歳定年説などもあるのが現状。社会活動家としても、自分の好きなことだけでも生きていけません。
これらの課題をセルザチャレンジで、ソーシャルブランドで、具体的に解決していきたいと思います。
そしてぜひその先進ケースを今後多くの方に見ていただき、お力を得られれば素晴らしいです。
昨夜は非常に刺激になりました。また機会があればいろいろな方とお話しできたらいいなと思います。
そして世界中の悩める同志と語り合ってみたいです。