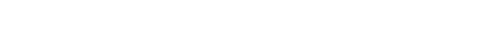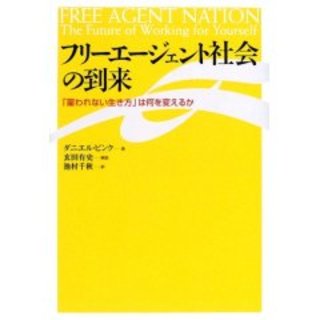以前に薦められて購入し、つん読になっていた本。
7年前にアメリカで出された本ですが、未だ新鮮な印象を受ける内容でした。
~「知識労働者は再び生産手段を手にするようになった」
タイムマシンに乗ってトーマス・ジェファーソンが最初の国税調査を行った1790年のアメリカに戻ってみよう。
職人や農民、零細な商人が大勢いる。大半の人にとって大組織など不要であった。産業革命が起こるまでは生計を立てるのに必要な道具類のほとんどは安価で手に入れることが出来たし、巨大なものではないので自宅に置いておけた。
職人や農民、零細な商人が大勢いる。大半の人にとって大組織など不要であった。産業革命が起こるまでは生計を立てるのに必要な道具類のほとんどは安価で手に入れることが出来たし、巨大なものではないので自宅に置いておけた。
しかし産業革命後は、こうした道具類は個人では手が出ないぐらいに高価になり、一人で操作するには複雑になり、家に置くには無理なほど大型になった。(蹄鉄はハンマーで自宅倉庫で作れるが、T型フォードはそうはいかない)。
こうした変化の結果、職場は巨大な道具倉庫のような性格を持つようになった。
管理者は決まった時間になると道具倉庫を開け、労働者が皆で一緒に道具をきちんと使うように見張り、時間になると倉庫を閉めて労働者を家に返す。
それまで一体であった資本と労働が分離したのだ。資本家が道具を所有し、労働者は巨大な機械が生み出す莫大な利益から少ない分け前を受け取るようになった。
管理者は決まった時間になると道具倉庫を開け、労働者が皆で一緒に道具をきちんと使うように見張り、時間になると倉庫を閉めて労働者を家に返す。
それまで一体であった資本と労働が分離したのだ。資本家が道具を所有し、労働者は巨大な機械が生み出す莫大な利益から少ない分け前を受け取るようになった。
しかし、状況は再び産業革命前に戻ろうとしている。知識経済の生産手段は小型で安価、操作も容易であまねく普及している。
コンピューターが安価になり、携帯型の端末が普及し、どこにいても地球規模のネットワークに接続できるようになったおかげで、労働者は再び生産手段を手にすることが出来るようになったのだ。~
コンピューターが安価になり、携帯型の端末が普及し、どこにいても地球規模のネットワークに接続できるようになったおかげで、労働者は再び生産手段を手にすることが出来るようになったのだ。~
パソコンとインターネットの普及で、第2の産業革命といわれるぐらい大きな変化がビジネス界に起きていると思います。
仕事の内容にもよりますが、地方の会社では都会に店を出さなくても現地からインターネットで商品を販売できる、海外ビジネスでは高価なテレックスが不要になり各個人がどこにいても自分のパソコンで世界の人とメールや電話ができる、など以前に比べて小さな資本や個人の努力で事業が行える環境になってきています。
また、組織がもつ弊害も少しづつ減ってくるのではないかと思います。
振り返れば自分も大企業に始まり中小企業、最後は数十人の小さな会社と企業に10数年おりましたが、小さくなればなるほど、仕事・成果の割りに人数が多いこと、大組織的思考による物事の進まなさ、形骸化朝礼、移動も含めて時間を使う休日全社員会議などが存在し、知的労働生産性の低下とストレスを感じました。
知的作業のインプットアウトプットは、集まって顔を合わせて話す重要な局面は別として、パソコンとインターネットで大半の部分をカバーできます。
今後は、各個人が各自の生産手段を活用しプロフェッショナルとして有機的に関与していくような関係性や場が生まれていくことで、企業組織のあり方も変わってくると思います。
今後は、各個人が各自の生産手段を活用しプロフェッショナルとして有機的に関与していくような関係性や場が生まれていくことで、企業組織のあり方も変わってくると思います。
ボブ・ディランの「成功したと言えるのは、朝起きて、自分のやりたいことをやれる人だ」という言葉が出ていました。
確かにそうかなと思いました。
確かにそうかなと思いました。