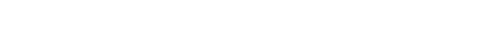さて、前回の全体フレームワークにおける④の事業領域・コンセプトの策定で、ターゲット(お客さん)を決めるところがありました。
ターゲット(お客さん)つまり、商品やサービスを使って欲しい、買って欲しい人を設定することです。
横文字では、ターゲティング。
今回はここでのポイントを書いてみようと思います。
誰をターゲットとするかということは非常に重要です。
例えば、「地球上の生物」をターゲットとするのか、「動物」にするのか、「人間」にするのか、「日本に住んでる人」にするのか、「横浜市に住む小学生」にするのか、「横浜市青葉区に住む小学校1年生の男の子」とでは、ターゲット数の大きさや具体性という話では大違いですね。
この世にターゲットきっちりを決めないで、いかにうまくいっていないことの多いことか。。
また、その逆の成功事例が多いことか。
みなさまも思い当たることがあるのではないでしょうか。
まず、ターゲットを設定するにあたり以下の4つことを念頭において考えてみましょう。
①対象の規模と成長性
ターゲットの人数や的の大きさはどれくらいよ?今後それって増えるの?購買力はあるの?競争相手ってどうよ?
②投資効果
そのターゲットに売るまで大変か簡単か?長期戦か短期戦か?儲かるの?やる価値あるの?
③自分の目標との整合性
そのターゲットって自分に合ってるの?それって本当にやりたいこと?
④自分のスキル・資源
いいターゲットであることは分かったけど、今の自分にできるの?お金あるの?決まってる自分の店の前を通るの?
ってな感じです。
(これ以上細かいウンチクは不要ですが、この本の44~45ページに昔書きましたので暇な時に見といてください)
ここでよくやる間違いが、消費者向けの製品メーカーが、消費者のことをあまり考えず、問屋さんや小売店などの流通上の自分の取引先をターゲットとしてしまう例。
ターゲットはあくまで、製品等を使うエンドユーザーですからね。
自分の製品を流通してくれる問屋さんや小売店さんは、製品を消費者に届けてくれる流通上の協力者・パートナーであって、ターゲットに設定すべきではありません。
これをやっちゃうと、取引先の問屋や小売店に商品を納めて売り上げをあげてなんぼ、
結局消費者には売れなくて、流通在庫が溢れて返品になるか安売りされるか、倉庫に在庫はたまる一方で現金化できず・・・・トホホの結果が。
気をつけましょう!
次にターゲットを設定する際、最も重要なポイントを言います。
「具体的なターゲット像を作る」
これです。
つまり対象が人間ならどういう人か、企業ならどういう会社か、とことん具体的にイメージすることです。
一人に売れないものは、全員にも売れないものです。
一人も喜ばないことは、世界中にも喜ばれないことです。
使ってくれるあの人とあの人のことを思い浮かべて、昔からモノって作られてきたはず。
マスプロの時代になりましたが、それは同じことです。
例えば対象が人の場合、
住んでる場所、出身地、年齢、性別、年収、通ってた学校、住んでる家、働いている所、勤務時間、起床時間、就寝時間、家族構成、趣味、スポーツ、顔立ち、髪型、部屋の雰囲気、部屋に張ってある写真やポスター、読んでいる本、好きな音楽、乗っている車、着てる服のブランド、良く行く美容院、使ってる化粧品、よく行く店、よく見るテレビ、使ってるパソコン、使ってる家電、それら物品のそれぞれの購入場所、友達の数、持っているCDの枚数、、、、、、
とことんまで、リアルに想定・設定します。
実在するかしないかも良く考えながら。
ターゲットモデルがいると分かりやすいですよね。
芸能人とか影響力のある友人とか、いけてる自分も含めて。
もろもろの具体的な設定は何に良いかというと、のちのち製品やサービスを売る場所、伝える場所が簡単に決まってくるのです。
その後の戦略が容易に・具体的に立てられるということ。
例えば、そのターゲットにした人のために作った製品は、その人の行く店に置いてもらって、好きなブランドとコラボさせて、よく読む雑誌に載せて、その友達コミュニティで話題になって、通勤電車の社内テレビで乗っている時間に広告ビデオ流して、さらに美容院でも何気においてあるし、良く行く洒落たレストランにもアメニティとして置いている・・・・状況を作るなどなど具体的に打ち手が考えられますよね。
逆にはっきりしていないと、どこで売ったら良いのか分からない、どこで宣伝したら良いのか分からない、これじゃ売れないでしょう。
このターゲットの具体的な設定がうまくいけば、後がホントにラクになります。
さて、おまけで実践で使えるターゲット設定上の参考例を紹介しときます。
(特に大人に趣味のものやファッション系製品や化粧品、伝統工芸品などの付加価値の高い製品やサービスを売っている人向け)
「雑誌を参考にする」
雑誌によって、ターゲットとなりそうな人は何人ぐらいいるのか、
そして彼らは、どんな、モノ、ネタ、ブランド、お店、サービス、テイスト、デザイン、雰囲気、考え方、価値観などを支持しているのか
が分かります。
雑誌って、同じ趣味や趣向の人が買うものですよね。
ファッション誌から週刊誌、業界紙などありますが買う人はみんな共通の目的や価値観を持っている。
いわゆる同じ目的や価値観によって出来上がった集団な訳です。
なんとなくありますよね。
女性だと特に「CanCan」読者の人と、「SPUR」の人は雰囲気違うし、「VERY」の人と「OGGI」の人も違うなんて感じ。
最近はネット社会や趣味の多様化が進んで地域や年齢でターゲットが括りにくく、価値観による分類・括りのほうが分かりやすくなってきています。
雑誌は、そのターゲットが持つニーズに応える内容で編集され、その独自のコンテンツを支持する人が買っている。
そして、雑誌は支持を得られないと継続せず廃刊となり、内容はニーズに合わせて毎月進化しながら存在しているわけです。
しかも、マーケティング資料からその雑誌の発行部数は分かりますからね。
たとえば女性ファッション誌だったら、
an・an(37万部)、RAY(23万部)、ELLE(22万部)、OGGI(22万部)、家庭画法(19万部)、STORY(19万部)、FIGARO(18万部)、INRED(18万部)、クロワッサン(17万部)、BAILA(16万部)、DOMANI(16万部)、流行通信(15万部)、SPUR(13万部)、PRECIOUS(13万部)、婦人画法(11万部)、FRAU(10万部)、GINZA(10万部)、VOGUE(9万部)、装苑(6万部)、マリクレール(5万部)・・・・
実売数とは違いますが、大体の多いか少ないかが分かればOK。
ファッション製品だったら、どんなテイストにして、どんなコンセプトにしたら受け入れてくれてくれそうな人はどのくらいか?という感じであたりが取れると思います。
つまり、それぞれの雑誌の事業領域・コンセプト(ターゲット・ニーズ・独自能力)とその結果である発行部数を参考にすることで、自分たちのシュミレーションができちゃうということです。
雑誌の発行部数等が載っているこの本は使えますよ!
広報・マスコミハンドブックPR手帳〈2007〉
その他、「ミクシーのコミュニティーのメンバー数」や「グーグルの検索結果件数」、「ターゲットにイメージする芸能人のファンクラブの会員数」なども参考になりますね。
いろいろなものを参考にしながら、あたる確率の高い具体的なターゲットの設定にチャレンジしてみましょう!