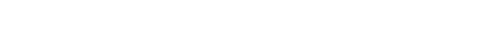地方において地場産業や伝統工芸などの再生についてのお仕事や、講演の講師をさせていただく機会があります。
状況として多いのは、数百年にわたり続いてきた伝統的地場産業が衰退の危機に瀕している状況です。
機能としてのみの製品の役割は、最新技術の出現により代替製品にとって代わられており、「芸術品」としての付加価値で生き残っている製品が多い状況。
例えば、「わらじ」という歩くために足を保護する機能を持った履物がありましたが、今やスニーカーや革靴、サンダルに取って代わられて流通市場で見る機会は少ない現状です。
伝統工芸で多いのは着物などの布もの、食器、籠やおもちゃなどが多いですが、それらの機能での優位性はとっくに新技術製品に明け渡し、今は「芸術品」などに昇華しきれたものしか市場に存在していません。
一方、今日存在する生き残った製品は数百年間という長い間人々に感動を与え続け、時代に淘汰されずに人から人に伝えられ、息づいてきた「感動の証明」であると思います。
機能を越えたところにある付加価値、「歴史」や「伝統」、「物語」、そして「感動」は簡単に出来るものではありません。
またその感動の灯火を、私たち世代で消してしまうのか次世代まで伝えられるのか、非常に責任重大なことと感じています。
日本人は、「匠の民」といわれています。
第二次世界大戦後、経済を再興させたのはソニーや松下、トヨタなどの製造業であったと思います。
今の世界においても、どの業種で日本人が活躍しているか考えると、金融や情報テクノロジーなどの得意なこともありますが、「ものづくり」はオハコの気がします。
そんな「匠の民」としての自負を持って、地場産業・伝統工芸の再興を非力ながらお手伝いしていきたいなと常々考えています。
私たちが受け継いできた「感動の灯火」を消さないように。
当たり前と思っていることは見つめ直せば実は凄いこと。
テクニックや手段や事例は二の次。
初めての講演のときは、代々引き継がれたその感動を再認識していただくことを大きな目的と心がけています。
そうして再認識した数百年の感動ストーリーの伝え方はいくらでもあります。
手作業が多くを占める伝統工芸の仕事は、自分のやるべき雇用創出の仕事への接点も感じ、非常にやりがいのあることと思って取り組んでいます。