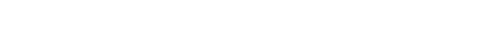夏休みの季節となりました。
暑かったり雷が落ちたりと不思議な天気ですね。
さて、昨日一昨日と真夏の緑あふれる東北は会津若松に行ってまいりました。
会津若松といえば白虎隊や猪苗代湖で有名ですが、その中でも世界的にも有名な伝統工芸品で会津漆器があります。
ウルシを塗った工芸品で、よく見かけるものは盃やお椀、重箱、お箸等がありますね。
会津での漆器産業は、古来より漆器文化があった会津に、今から約400年前に織田信長の義理の息子である蒲生氏郷が秀吉の天下統一後に会津に来た時、上方から多くの漆器職人を伴い手工業の奨励等を盛んに行ったことで発展したといわれています。
蒲生氏郷
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%94%9F%E6%B0%8F%E9%83%B7
今回は、この伝統業芸をやられている職人の方々が「会津漆器をどうやって売っていくのか」ということを会津若松市とのプロジェクトを行っており、そのお手伝いで呼んで頂きました。
横浜から電車とバスを乗り継いで約5時間で会津若松市に到着です。
会場には職人さんのほか市役所の方や調査会社の方々もいらっしゃって、熱気ムンムン。
「具体的にどうやって売っていくのか」について短い時間でしたがお話させていただきました。
皆様とても熱心で、こちらも何が何でも成功させたいと感じる素敵な会となりました。
会津漆器職人の方々(会場で一次会をしていただいた後で皆ほろ酔いです)
懇親会では一次会、二次会も含めてたくさんお話しし、みんなでたくさんの面白い仕掛けやアイデアが出すことができました。
会津漆器、これからちょっと面白くなりますよ!
今後の事業開発、デザイン、プロモーション、チャネル等、動きに注目しておいてください。
大盛り上がりです。(北国の人がこんなにファンキーとは思いませんでした)
次の日は、急遽いくつかの工房をご案内いただけることになりました。
まず、はじめはガラスに漆を塗るという新しい試みをされている千藤の加藤さんの工房です。
市中から少し離れた山の上の渓谷の横に工房があります。まさにトトロの世界。
ガラスと漆の組み合わせは珍しいですね。涼しげな感じで洒落ています。
ホームページでも作品等が見れますので、見てみてください。
http://www.senfuji.com/
http://www.art.a-vst.jp/sakka/ka/ka/ka.html
古民家を改装して工房にしていますが、面白い農具等がたくさん残っています。
壁には、古来から伝わる日本の薬草と効能の表が張られていました。ハーブと同じ!
柿渋を塗ったカゴもいい感じですよね。
次にお邪魔したのが、木地職人である三浦さんの工房です。
職人の方々は分業体制があり、木を加工する人、漆を塗る人、絵を入れる人とそれぞれ専門があるとのことです。
木は、会津でとれるトチ、クリ、サクラ、ホウ等を用途にあわせて使い分けます。
さて下は、お椀を削っているところ。
刀は何種類も自作して使い分けています。
荒削りした状態で、約1年乾燥させます。それは、乾燥によって木が変形するためです。
下の写真もはじめは真ん丸に削っていたものですが、楕円形になっています。
一方、一年以上長い間置いておいても今度は割れてきたりして材料がダメになってしまうとのことです。
ロスが出る材料ということで、在庫管理も大変ですね。
これだけ大きな木ですが、真ん中は割れやすい等の制約があり、木から取れる部分は非常に少ないのです。
この木が育つ時間や手間ひまを考えると、本当の意味で価値のある贅沢なものと感じます。
三浦さんの作品です。
塗りは、塗り職人さんに基本的には任せますが、ご自身で塗られているものもあります。
質感が良くて重厚でありながら繊細さに品格があります。
ホームページ
http://www.aizu-furusato.com/pfaizu/guide/iimono/html/miura.html
http://www.art.a-vst.jp/sakka/ma/mk3/mk.html
さて次は、塗り職人の儀同さんの工房です。
会津若松のおうちは蔵造りが多く、実は蔵で有名な喜多方よりも数は多いそうです。
中はひんやり涼しく、イタリアの石の家と似ています。中身も非常に美しい漆を使った飾りが多いです。
塗りの仕事場。埃を嫌うため隠して乾燥するための押入れの前で作業します。
漆塗りに使うのは、実は女性の髪の毛で作った筆!
男の髪は平べったい断面だが、女の髪は真ん丸の断面で、それが適しているとのことでした。
驚きました。
このように押入れの中で乾燥させます。
ただ、数十分間の間隔で動かさないと塗料が平均的な厚さにならないということで、中身の固定枠が自動的に動くようになっています。ハイテクですね。
これらは原料の漆の写真。
上が中国産で6万円ぐらい、下が日本産でその6~7倍。しかし、日本の物のほうが明らかに美しく仕上がるとのことです。
これも驚いたのですが、漆は漆の木が15年かかってある程度の大きさになったとき初めて牛乳瓶200ML一本分が採れ、それでその木は終わりで伐採だそうです。ゴムみたいに何度もとれないらしいです。
そりゃ貴重品ですよ!
儀同さんはシチズン時計とコラボレーションで限定の腕時計を作っています。
ワールドビジネスサテライトでも限定300本は即完売とのこと。
http://www.citizen.co.jp/release/05/050727cp.html
http://www.aizu-city.net/waza/aizu/kaiin/gidou/gidou.htm
http://www.kougeishi.jp/kougeishi.php?kougeishi_id=502718
最後にお邪魔したのは、絵付け職人の山内さんの工房です。
細い筆で繊細な図柄を描いていきます。非常に集中力の要る作業です。
トラディショナルな柄から、斬新なデザインまで広がりがあります。
本当に良いものというのは、じっくり丁寧に時間をかけて作られています。
決して派手ではないですが、その手間や想いの一つ一つが作品から漂ってくるものです。
http://homepage3.nifty.com/onnmakie-yamauti/index.htm
http://www.kougei.or.jp/crafts/0506/d0506-5.html
http://www.kougeishi.jp/kougeishi.php?kougeishi_id=504812
今、このあらゆるモノに溢れ返っている日本で、今までのような買って捨ててを繰り返さない、こういったこだわりの一生付き合える本物を探している人が多い時代になってきました。
ここ10年ぐらいで中国製の安い雑貨等が出回り、景気も悪かったので値の張る日本のトラディショナルな伝統品にスポットが浴びない期間がありました。
しかし、家の中を見渡してみると、中国製品に日本のブランド名を印刷しただけのこだわりの少ないモノで、安くて少しおしゃれに見えたから買ったけど、邪魔になってもういらないモノってありますよね。
半年ごとに新しい製品が大量に発売されて、古くなったのが大量にディスカウント販売されて、、、いくら安くてキャッチーでもそういうやり方のモノはもうお腹いっぱいです。
まだ使えるモノも、もういらないけどフリーマーケットに出すまで保管しておく場所はないし、面倒だとついついゴミに捨てちゃう。最初はもったいないと思っていても、どんどん捨ててる営みはそろそろやめたいと思うようになりました。
やっぱり限られた一生、手間ひま心をこめて作られる良いモノと暮らしてみたいです。
そして今、長かったデフレが終わろうとしています。
まさに今が新たな時代の夜明けなのです。
今回ご縁があって、今まで全く知らなかった会津の心、会津漆器に出会うことができました。
その生き方への挑戦に惚れました。
これから、この会津漆器の世界について、知らない人に少しずつでもお伝えしていければと思います。
カッコいいですよ!会津の漆器は。
あと、会津名産の蕎麦や味噌田楽、馬刺しに日本酒とご馳走になりました。
ホントうまかったです!ありがとうございます。
ファンであるサンボマスターも会津出身ですし、もう「会津最高!」
これから会津漆器プロジェクトすごいことにしたいと思います。
好ご期待!