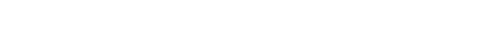「Seminare e Vievere」
セミナーレ エ ヴィーヴェレと読むこの言葉は、イタリア語で「種を蒔いて生きる」という意味です。
シンプルな響きの中に深い人間の営みを表現している言葉です。
さて、以前にお仕事をしていた有機栽培農業組合では、手間ひまが非常にかかる特殊な有機栽培を行っていました。
これはご存知の方も多いですが、ルドルフ・シュタイナー博士という人智学の祖が1920年代にドイツで考案した、どうしたら痩せた土地でその土地の持つ力を最大限に引き出して、たくさんの収穫を得るかという方法で、ドイツをはじめヨーロッパや北米などにはメジャーな有機栽培です。
基本的には土中の有機物の力を借りて植物の発育を促進するというものですが、月の満ち欠けなどのカレンダーにあわせて農作業を手作業で行い、普通の農薬栽培の5倍以上の手間ひまがかかる大変なものとのこと。
この現代になぜそんな昔の農法が残っているかというと、「効く!」からということらしいです。
実際その農業組合でも、当初は一般的な有機栽培方法を採っていたのが、ある年この農法を試してみたところ、「オッタマゲタ」らしく組合員全員で転向したという歴史があります。
保守的で、ドイツ嫌いのイタリア人が全員で始めてしまうというのは少し驚きですが、そんなことを考えるとやっぱりホントに効くんじゃないかなと思います。
しかし、この有機農法による作物の栽培ですが、作業量は普通の栽培方法の5倍と先ほど書きましたが、売れる金額は1.2倍ぐらいとのこと。
そりゃそうですよね。普通より5倍の値段の野菜やハーブなんてみんな買わないだろうし。
ただ実際、トマトやキュウリはすごく美味しいいですね。ハーブなんかも香りや見た目でも明らかに違いはあります。
手間は手作業でそれなりにかかる。それほどは儲からないが、愛情を込めて育てれば育てるだけ本当に他のものとは差別化できる美味しい、よいものは作れる。
最近は企業のCSRの一環として障がい者の法定雇用率の達成に向けて、動きは出てきています。
しかし、個人によって状態は異なりなかなか企業側とニーズがマッチしないこと、やれる仕事も限られており絶対的に求人は少ないこと、地元に募集企業は少なく満員電車に乗って郊外から都心の企業に通えない人も多いこと、やりがいの見える仕事があるのかわかりにくいこと、、等々たくさんの現実として乗り越えにくい要素はたくさんあります。
スワンベーカリーなど成功している事例は、ハンディを持つ人のための仕事と仕事場を、地元に密着して、作り出している事業です。
家の近くであれば通えるし、そのために作られた仕事を、そのそのために作られた仕事場で行う、得意なことを仕事とする。
キーワードは、「仕事は自ら作り出す、得意なことをする、地元密着」という感じでしょうか。
さてさて先ほどの、手間はかかるが良い作物のできる有機農法で、通えるそれぞれの地元で、地道に丹精を込めて植物を育て、できたハーブや野菜を販売する仕事を作る。
小さな種がある。それをみんなで蒔いて育てる。注いだ愛情や手間ひまによって根は深く地に生える。そして実りと新たな種ををもたらす。実りを誰かが喜び消費が起こる。作業が経済活動となり仕事になる。作るものは食べることができ生きる糧となる。次の循環を生む種を蒔く。
「種蒔いて生きる」
この事業のお手伝いをさせてもらうことにしました。