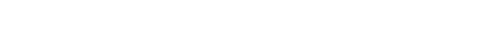全体のフレームワークのプロセス④事業領域・コンセプトの策定(やることを決める)は、
「ターゲット(お客さん)、ニーズ(こうなったらいいのにな)、独自能力(自分しか出来ないこと)の切り口で組み立てると外さない」
と説明しました。
そして前回「ターゲットはより具体的に」と説明しましたが、
「ニーズや独自能力もより具体的に」です。
ニーズの把握については、何度も言いますが「現場100回」。
ターゲット(お客さん)は、何に困っていてどうしてあげたら喜んでくれるのか、見て聞いて観察して、自分も経験して、し尽さないといけません。
例えば、東京駅を朝晩利用する30代の男性ビジネスマンをターゲットとして駅ナカ事業を始めようとした場合、最低でも10日は朝晩張り込み観察が必要ですね。
ターゲットは、何時に何人通ったか、どんな人達なのか、どんな服を着ているか、何をしながら歩いているか、一人か夫婦一緒か、どんな顔をして歩いているか、視線はどのように動いているか、動線はどのようにとったか、駅売店で何を買ったか、近隣にその時間どんな店が開いているか、競合サービスはどんな感じか、そこでどんなニーズがありそうか、
ということをとことんターゲットの立場になって調べ考え抜くプロセスが必要です。
そして初めて、ニーズ(こうなったらいいのにな)というものが分かります。
独自能力(自分にしか出来ないこと)については、よく考えて製品やサービス、またその提供の仕方を具体的に設定しましょう。
例えば自分のお店の隣に強烈な激安チェーン店やブランドショップが出来ても絶対負けないような勝てる個性を具体的に。
自分の強みを活かして、手段を色々組み合わせたらオンリーワンが必ずできると思います。
そして最終的に以上の、
事業領域・コンセプトの策定(やることを決める)として、
ターゲット(お客さん)、ニーズ(こうなったらいいのにな)、独自能力(自分しか出来ないこと)の要素を入れて、
一文にまとめます。
「~~~をターゲットに、~~~のニーズに対して、~~~を~~~で提供する」
という感じ。
これは俳句のようなもので、何度もやっているうちにブラッシュアップしていきます。
書き方例で、新人A君の場合は、
「○○課の先輩5人をターゲットに、日々のアナログな見積もり作成に膨大な時間が割かれ、何とか業務を効率化したいというニーズに対し、社内で唯一マクロの分かる自分が現状業務を効率化する仕組みを作成して提供する」
なんて具合で。
やってるうちに慣れてきます。
気楽な感じで練習してみましょう!
この事業領域・コンセプトの策定がうまく出来ると、お客さんをはじめ社内外の関係者、その他多くの人に「なるほどね!」と納得してもらえ、話は早く進むし、本当に喜ばれるし、という感じになります。
このプロセスは、製品をつくるのはもちろん、デザインをやるにしてもサービスを考えるにしても、食器でも雑誌でも使えます。
セルフマーケティングも重要。
まず、自分自身のコンセプトを作ってみても面白いかもしれませんね!