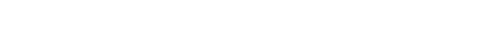「社会的弱者による製品づくりに学ぶ、世界でオンリーワンになるためのマーケティングと経営」
~弱みを強みに転じる生き残り方~
3.事業を成功に導くには
⑦共感者のみがお客さま 共感を得られるお客さまを探す
共感してくれる人がお客さま
授産施設において新しい製品を企画し、販売していくにあたって気づくことがあります。それは製品として他との差別的優位性を出しにくい製品であればあるほど、共感に訴えて売らざるを得ないということです。
セルザチャレンジのプロジェクトでは、できれば一般社会とのつながりが薄い授産施設で働く方々の製品を一般市場に展開、今までのバザーだけではなく都心部の百貨店やおしゃれなショップで販売することで、仕事に携わった人が社会とつながり、そして本人の活動が都心の小売店のスポットライトが当たる売り場に並ぶことで「~~さんの作ったものがあのお店で売っている」という家族にわかりやすい取り組みを目指してきました。
ビジネスのプロであるプロジェクトメンバーは、洗練された売り場に並ぶ一般製品に負けないようなコンセプト、素敵なデザイン、価格、品質を目指して同等の製品に作り上げています。
しかし、その同等である一般製品から、障がい者の手によるものを選ぶお客さまはどのような人だったしょうか?その製品や取り組みをに共感し、応援し、製品を購入してくれたお客さまは?
ほとんどが障がい者とご縁のある人です。
またこういった経験があります。前述した「陸前高田 冰上 福幸梅」の販売に際しては、都心の高級スーパーや百貨店の食品売り場などといった、梅干しとしてのプレステージとなる売り場への導入も企図していました。
それは、地方の施設の現場とそこで働く障がい者と、東京のピンの売り場を結び付けることで、やりがいやニュース性、ブランドイメージ、施設の取り組みの革新性を得たいと思ったからです。そしてそれまでは自分自身も障がい者が作るものでも、最高の売り場に置くことにこだわり、意地になって進めてきた感じもありました。
セルザチャレンジメンバーによるクオリティの高い広報活動も行い、また力を合わせて各々宣伝し、様々なイベントでの紹介も行いました。
戦略はしっかり立てていましたが実際に営業活動を始めた際、梅干しを持ってご紹介などをいただきながらターゲットである高級スーパー・百貨店に営業に伺いましたが、品質の安定性その他の要因も含めて惨敗でした。7月に発売した梅干し2,000パックは、事務所に積み上がり、毎日何とかしなければと焦りがありました。自分自身にとっても初めての商材で難儀しました。
マーケティングのプロフェッショナルであり、ターゲットを定めて戦略をつくり、最適なマーケティングミックスで提供せよ、と講釈を垂れている者が全く面目のないことです。
高級店への導入に躍起になっていた自分が、とにかく売らないとまずいと思った時に、救いの手を差し伸べてくれた人たちがいます。
それもほとんどが障がい者とご縁のある人です。
それは、バザーを行うという東北以外の福祉施設、授産製品のお店を経営されている人、今まで障がい者支援をともに目指し一緒に仕事をしてきたパートナー企業の経営者、障がい者の雇用創出に理解のある人、学園祭などを実行する社会貢献に興味のある学生さん、セルザチャレンジメンバーの知人、などでした。
そして、瞬く間に事務所に積まれていた梅干しは完売となって無くなったのです。
分かり合える人と共に生きていく
今まで、授産製品を一般流通で、一般製品と並べて負けないように、品質や価格で勝負し、一般消費者に広く販売する、ことにこだわってきた自分に少し悟りが得られました。
ベストを尽くしてもわかってもらえない人より、より分かっている人に先に販売したほうが双方ハッピーである、ということです。
自分自身も家族に障がい者がいなければ、授産製品などきっと全くどうでもよいことだったと思います。自身が最貧国で出会う人のために製品づくりを手伝う機会がなければフェアトレードなんでどうでもよいことだったと思います。
それよりも、そういった取り組みを応援したいと欲している人たちがいるのです。その人たちにコミットした製品やサービス、取り組みを行ったほうが、マスに向けたメッセージより実が得られると思います。マスもよいですが、コアな共感者のニーズを満たすことが先です。言い換えれば既存顧客での売り上げを上げることが先です。
障がい者に関係する人は日本に何人いるでしょうか?1,000万人近い手帳を持つ人にその家族、福祉の現場で働く職員の方々。それを考えると、最低3~4千万人の人が障がい者に関係する人ではないでしょうか。これをしっかりカバーできれば市場規模としては十分すぎるターゲットです。
福祉の現場の製品を目立つ都心の売り場でも展開します。そして福祉の現場を知らなかった新たな人を製品を通じて共感者としていきます。一方、共感者に確実に届けるためにバザーや福祉ショップなどでも販売していきます。この組み合わせが一つの答えと思います。
手堅い成功には
そこで、授産製品を施設職員の皆様が自力で販売していく際は、とにかく身近な理解者、共感者から販売していくことをお勧めしています。そのほうが、まだ見ぬ都会の大きなお店に並んで買われるか買われないかということよりも、確実だからです。
それは、すでにその取り組みの応援者であり、共感者であるからです。その人が喜ぶような製品をつくって、買いやすいチャネルで販売する。バザーでもよいです。そういった取り組みがまず大切です。
地域に根差した製品であれば、近所の道の駅も良いチャネルです。近所の町のお店で扱っていただけるよう一軒一軒訪ねてみてください。東京の県人会や県産ショップもよいです。
地元の地方紙やコミュニティ誌に案内してみてください。
競争力のある製品に仕立てたうえで、さらに共感でこの製品を選んでいただく。
宣伝告知もフェイスブックなどを通じて、知人友人からです。自分自身を応援してくれる仲間が先です。ソーシャルメディアの発達で、同じ悩みや考え、感覚を持つ人がつながりやすい時代になっています。
まずは身近な共感者から。そしてその共感者をどんどん増やしていく。
手堅い成功にはそのような視点が大切と考えています。
つづく